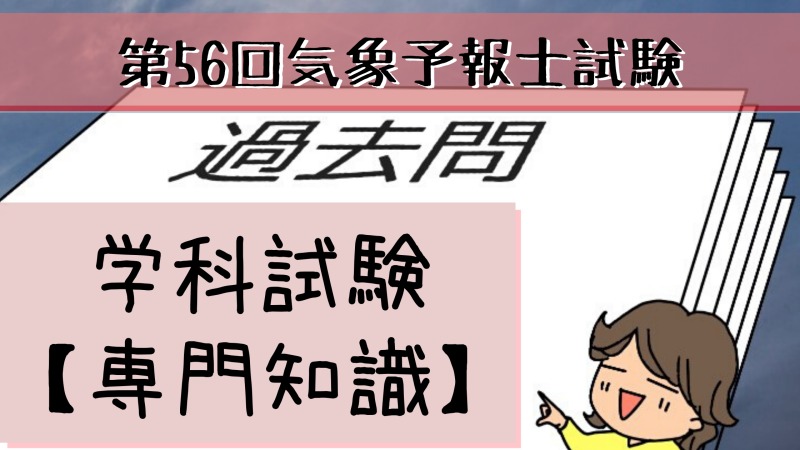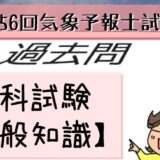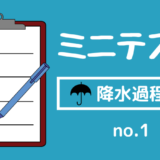この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
令和3年8月の第56回気象予報士試験の学科専門知識の問題を、
あなたが次に似たような問題を解く時、「ヒント」となるような内容を目指してます!!!

この記事は、令和3年8月の第56回気象予報士試験の学科専門の問題と解答を持っている人向けの内容です。
※私個人の試験問題を解く時の思考例です。(気象業務支援センターとは関係ございません。)
問1:降水の観測や雨量計
気象庁が行っている地上気象観測における降水の観測や雨量計について述べた次の文(a)〜(d)の正誤について下記の①から⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)「降水量」とはある時間内に地表の水平面に降った雨・雪などの量であり、降水が地中にしみ込んだり他の場所に流れ去ったりせずに地表面上を覆ったとしたときの水の深さ(雪などの固形降水の場合は融かして水にしたときの深さ)で表す。
(b)アメダスでは雨水が転倒マスに一定量(0.5mm相当)入ると転倒する構造の雨量計を用いて転倒した回数から雨量を観測している。
(c)雨量計に隣接して建物や高い樹木などがあるような環境では、雨滴や切片の捕捉率が下がるなどして、観測精度が低下する。
(d)雪などの固形降水が積もって地面を覆っている状態を「積雪」といい、稀に夏季にひょうが積もって「積雪」となることがある。
① (a)のみ誤り
② (b)のみ誤り
③ (c)のみ誤り
④ (d)のみ誤り
⑤ すべて正しい
④ (d)のみ誤り
「降水量」とは、降った雨が土にしみ込まないと仮定して、所定の時間で単位面積あたりに何ミリメートルの深さ(高さ)まで降水が溜まるのか、を意味します。▶︎用語集「降水量」
だから(a)の「『降水量』とはある時間内に地表の水平面に降った雨・雪などの量であり、降水が地中にしみ込んだり他の場所に流れ去ったりせずに地表面上を覆ったとしたときの水の深さ(雪などの固形降水の場合は融かして水にしたときの深さ)で表す。」は正しい。
気象庁で使用しているアメダスの転倒ます型雨量計の「ます」の容積は 0.5 ミリ相当となっています。
だから転倒ますの転倒回数で 0.5ミリずつ観測した降水量が増えていきます。
- 転倒 1 回 → 0.5 ミリの降水量
- 転倒 2 回 → 1 ミリの降水量
だから (b) の「アメダスでは雨水が転倒マスに一定量(0.5mm相当)入ると転倒する構造の雨量計を用いて転倒した回数から雨量を観測している。」は正しい。
降水量の観測は、地形や周囲の構造物によって発生する「風の乱れ」の影響を受けやすいです。
特に隣接して高い樹木や建物があると、風と共に降水も遮られてしまう可能性があり、観測精度は低下します。
だから (c) の「雨量計に隣接して建物や高い樹木などがあるような環境では、雨滴や切片の捕捉率が下がるなどして、観測精度が低下する。」は正しい。
「雪などの固形降水物が自然に積もって地面を覆っている状態」を「積雪」というのはその通り。
でも「夏季のひょうや氷あられ」は、積もっても「積雪」とはいいません。
だから (d) の「雪などの固形降水が積もって地面を覆っている状態を「積雪」といい、稀に夏季にひょうが積もって「積雪」となることがある。」は誤り。