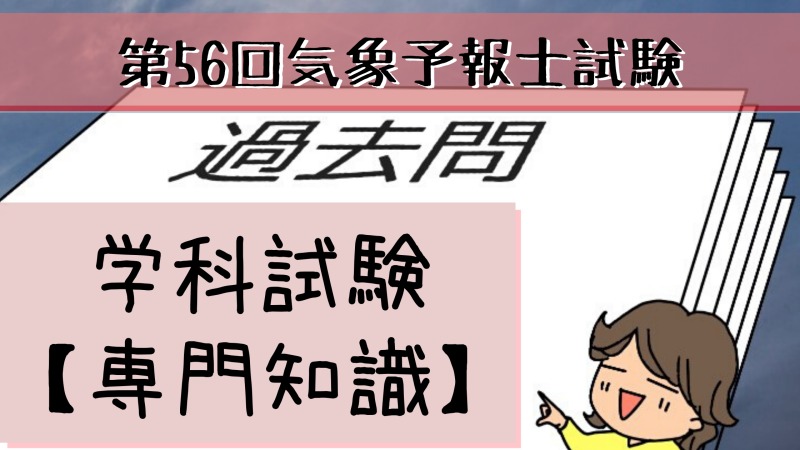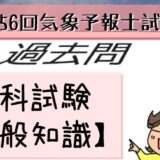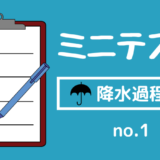この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問2:気象ドップラーレーダー
気象庁が行っている気象ドップラーレーダーを用いた観測について述べた次の文章の下線部(a)〜(d)の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。
気象ドップラーレーダーは、アンテナを回転させながら電波(マイクロ波)を発射し、半径数百kmの範囲内に存在する雨や雪を観測している。
(a)発射した電波が反射して戻ってくるまでの時間から雨や雪までの距離を測り、戻ってきた電波の強さから雨や雪の強さを観測する。
また、(b)戻ってきた電波の周波数のずれを利用して、雨や雪の動き(動径方向の降水粒子の動き)を観測し、降水域の大気の流れを捉えることができる。
また、最近導入された二重偏波気象ドップラーレーダーは、(c)水平方向と垂直方向に振動面を持つ電波(それぞれ水平偏波、垂直偏波という)を用いることで、(d)雲の中の降水粒子の種別の判別や降水の強さをより正確に推定することができる。
① (a)のみ誤り
② (b)のみ誤り
③ (c)のみ誤り
④ (d)のみ誤り
⑤ すべて正しい
⑤ すべて正しい
気象ドップラーレーダーは、発射した電波が戻ってくるまでの時間から雨や雪までの距離を測ります。→だから(a)は正しい〜。
また、戻ってきた電波の強さから雨や雪の強さを観測します。
さらに、戻ってきた電波の周波数のずれ(ドップラー効果)を利用して、雨や雪の動き(降水域の風)を観測します。→だから(b)は正しい!
気象庁では令和 2 年 3 月から、二重偏波気象ドップラーレーダーを導入しました。
二重偏波気象ドップラーレーダーは、水平方向に振動する電波(水平偏波)と垂直方向に振動する電波(垂直偏波)を用いています。→だから(c)も正しい!
水平偏波と垂直偏波を用いる二重偏波気象ドップラーレーダーは、雲の中の降水粒子の種別判別や降水の強さをより正確に推定することが可能です。→だから(d)も正しいのですー!!!!