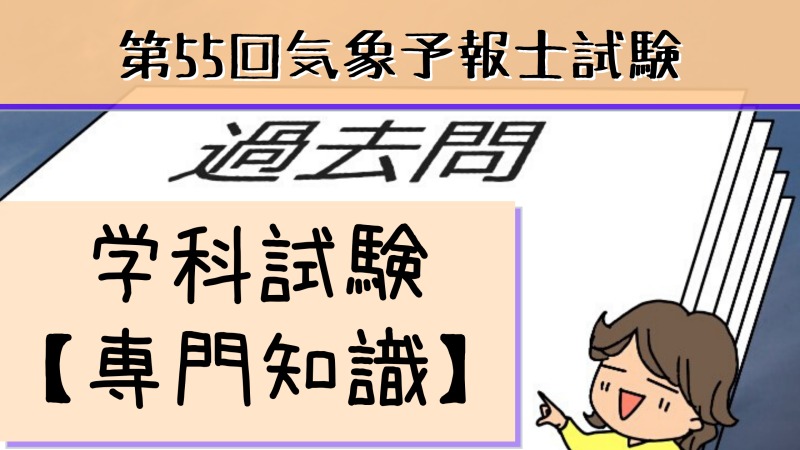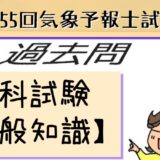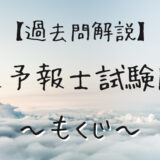この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問3:気象レーダーによる観測やその特性
問題文
気象庁が運用している気象レーダーによる観測やその特性について述べた次の文(a) 〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の1〜5の中から 1 つ選べ。
(a) ドップラーレーダーで観測した風のデータは,⻯巻の発生と関連の深いメソサイ クロンの検出に活用されている。
(b) 非降水エコーの原因となる電波の異常伝搬は,気温が高度とともに急激に上昇す るなど,屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生することが多い。
(c) 水平偏波と垂直偏波を用いる二重偏波気象レーダーでは,それぞれの反射波の振幅 の比から降水粒子の形状に関する情報が得られるため,雨や雪の判別が可能となる。
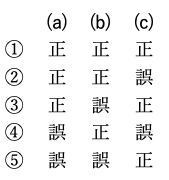
① (a)正, (b)正, (c)正
- ドップラーレーダーはメソサイクロンの検出に使われているか?
- 答え:使われている。
- メソサイクロンは竜巻の発生と関連が深いか?
- 答え:深い!
(a) ドップラーレーダーで観測した風のデータは,⻯巻の発生と関連の深いメソサイ クロンの検出に活用されている。」は正しい!
- 電波の異常伝搬は、非降水エコーの原因となるか?
- なる。
- 電波の異常伝搬は,気温が高度とともに急激に上昇するなど,屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生することが多いか?
- その通り!
だから(b) の「非降水エコーの原因となる電波の異常伝搬は,気温が高度とともに急激に上昇するなど,屈折率が高さ方向に大きく変化する場合に発生することが多い。」は正しい!
▶︎▶︎▶︎用語解説「異常伝搬」
- 水平偏波とは?
- 水平方向に波打つ電波のこと。
- 垂直偏波とは?
- 鉛直方向に波打つ電波のこと。
- 水平偏波と垂直偏波の2種類のを用いる気象レーダーのことをなんというか?
- MP(マルチパラメーター)レーダーという。
二重偏波レーダーともいう。
- MP(マルチパラメーター)レーダーという。
- 二重偏波気象レーダーは雨や雪の判別が可能か?
- 可能。

はれの
鉛直方向と水平方向から降水粒子を見ることで
「どんな形かわかる」→「雨か雪かわかる」
ってわけです。
だから(c) の「水平偏波と垂直偏波を用いる二重偏波気象レーダーでは,それぞれの反射波の振幅 の比から降水粒子の形状に関する情報が得られるため,雨や雪の判別が可能となる。」は正しい!