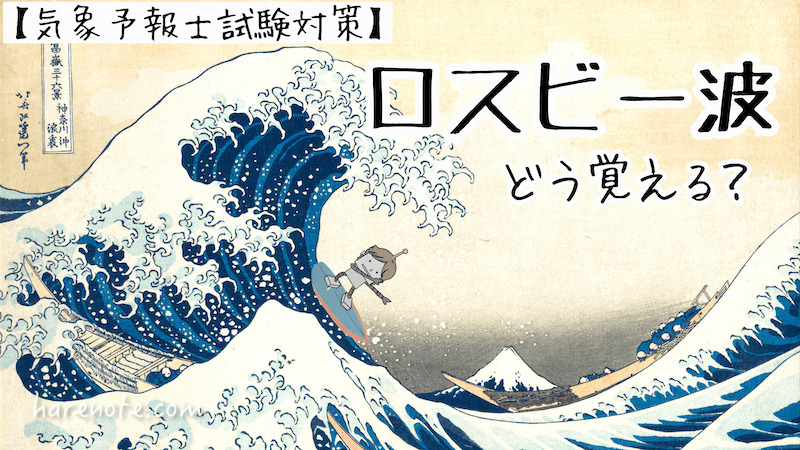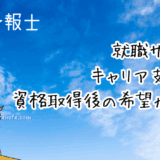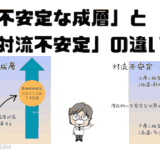この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

晴野の個人的なまとめノートですが、公開しています。
誤りなどのご指摘は、ありがたいので遠慮なくご連絡ください。
ここでは気象予報士試験に出題されることのあるロスビー波(Rossby wave)についてまとめています。
ロスビー波(Rossby wave)は、地球規模の大気の流れや海洋の動きに見られる、非常に大きな波のことで、地球の自転とコリオリの力によって発生する、大気や海洋の大規模な波動です。
気象学や海洋学において、「プラネタリー波」,「惑星波(planetary wave)」とも呼ばれ、地球の自転がその発生と伝播の鍵を握っています。
ロスビー波の基本的な性質

ここでは、ロスビー波の
発生メカニズム、伝搬の仕組み、規模と位置などのお話です。
コリオリ力の緯度変化(ベータ効果)地球が自転しているため、運動する物体には「コリオリの力」という見かけの力が働きます。
この力は、北半球では進行方向の右向きに、南半球では左向きに働きます。
重要なのは、このコリオリの力が緯度によって異なる(赤道で最も弱く、極に近づくほど強くなる)こと。
この緯度によるコリオリ力の変化(これを「ベータ効果」と呼びます)が、ロスビー波の発生と伝播の復元力となるのです。
もう少し詳しく言うと、大気の塊(あるいは海水)が南北に動こうとすると、コリオリ力の緯度変化によって、もとの緯度に戻ろうとする力が働き、これが波として伝播していくのです。
位相は西向き、エネルギーは東向き(偏西風に乗って)ロスビー波の波の山と谷(位相)は、ゆっくりと西向きに伝播します。
しかし、波のエネルギー自体は、上空の強い偏西風に乗って東向きに伝播していくのが特徴です。
イメージとしては、川の流れ(偏西風)に乗って葉っぱ(波のエネルギー)が流されていくような感じ。
葉っぱ自体(位相)は、川の流れに逆らってわずかに西へ動くような感覚です。
- 波長: 通常、数千km以上の非常に長い波長を持ちます。
地球を取り巻くように、数個(例えば5~6個)の波の山と谷が見られることがあります。 - 位置: 大気においては、主に対流圏中層から上層にかけて(特に偏西風帯)卓越します。
ロスビー波を発見したのは、スウェーデンの気象学者カール=グスタフ・A・ロスビーさん。
ロスビーさんによって1939年にその存在が理論的に導き出されたため、「ロスビー波」と名付けられました。
ベータ効果とは?
ベータ効果は、コリオリの力(コリオリのパラメーター)が緯度によって変化することを指します。

「ベータ効果」=「コリオリ力が緯度によって変わる」ってこと!
ベータ効果は、ロスビー波が生まれる主な原因です。
コリオリの力は、地球の自転によって、地球上を移動する物体に働く見かけ上の力です。
(北半球では物体を進行方向に対して右向きに、南半球では左向きに曲げるように働きます。)
このコリオリの力の強さは、緯度によって異なります。
- 赤道ではゼロです。
- 高緯度(極地)に近づくほど強くなります。
この「コリオリの力の緯度による変化」がベータ効果と呼ばれます。
ベータ効果は、大気や海洋の流れに南北の勾配(傾き)を作り出します。
この勾配が復元力として働き、大気や海洋が南北に振動する大規模な波、つまりロスビー波を生み出します。
簡単に言えば、【地球の球体であること】と【自転】という組み合わせが、【コリオリの力の緯度差】を生み出し、その結果としてロスビー波が発生するのです。
気象への影響と重要性

ロスビー波は、地球規模の気象現象に大きな影響を与え、長期予報や異常気象の理解に不可欠です。
上空の偏西風は、常にまっすぐ吹いているわけではなく、南北に大きく蛇行しています。
この偏西風の蛇行そのものが、ロスビー波の表れです。
蛇行の山では高気圧、谷では低気圧が形成されやすくなります。
ロスビー波の活動は、温帯低気圧や高気圧の発生・発達、そしてその移動経路に深く関わっています。
ロスビー波の振幅(蛇行の大きさ)が大きいときは、南北方向の熱や水蒸気の交換が活発になり、気象の変動が大きくなります。
ロスビー波が特定の場所に停滞したり、異常に大きな蛇行をしたりすると、移動性の高気圧や低気圧の進行を阻害する「ブロッキング高気圧」が形成されることがあります。
これにより、特定の地域で異常な猛暑、厳冬、長雨、干ばつなどが長期にわたって続く原因となります。
例えば、2010年のロシアの記録的な猛暑は、ブロッキング高気圧と関連が深いとされています。
PNAパターン(太平洋・北米パターン)で述べたように、熱帯域の対流活動(例:エルニーニョ現象)の変化がロスビー波を作り
そのロスビー波が中緯度まで伝播することで、遠く離れた地域の天候に影響を与える(テレコネクション)主要なメカニズムとなります。
ロスビー波の動向を正確に予測することは、数週間から数ヶ月先の長期予報や季節予報の精度向上に不可欠です。
ジェット気流の変動や異常気象の発生予測において、ロスビー波の解析は重要な役割を担っています。
偏西風とロスビー波の違いは?
偏西風は地球規模で西から東に吹く風そのものを指し、ロスビー波はその偏西風が南北に蛇行してできる大規模な波を指します。

偏西風とロスビー波はとても近い関係ですが、概念に違いがあります。
偏西風は、地球の自転と赤道と極地の温度差によって発生する、中緯度地域の上空を年間を通して西から東へ吹く恒常風です。
風速が特に強い部分はジェット気流と呼ばれます。

航空機が東向きに進むときに追い風になるのはこのためです。
ロスビー波は、地球の自転に伴うコリオリの力(地球の回転によって物体が曲がる力)が緯度によって異なる「ベータ効果」によって発生する、大気や海洋の大規模な波です。
この波は基本的に西向きに進もうとする性質を持っていますが、東向きに吹く偏西風に流されて、全体としては東向きに進むこともあります。
ロスビー波は、偏西風の中を伝わる波であり、偏西風の南北への蛇行そのものがロスビー波の現れです。偏西風が南北に大きく蛇行し、そのパターンが同じ場所に停滞すると、高気圧や低気圧がその場に留まり続ける「ブロッキング現象」が起こり、異常気象(猛暑、寒波、豪雨など)の原因となります。
簡単にいうと、川の流れが偏西風で、その流れが大きく蛇行している様子がロスビー波です。
偏西風という「流れ」がなければ、ロスビー波という「波」も存在しません。
ロスビー波は偏西風の蛇行部分か?

ロスビー波は偏西風の蛇行そのものを指すわけではありません。
偏西風が「川の流れ」で、ロスビー波は「その川の流れにできる大きな波」なのに、ロスビー波は偏西風の蛇行そのものを指すわけではない・・・どういうこっちゃ?ですよね。
イメージするなら、ロスビー波は蛇行の素みたいな感じ。
偏西風は、中緯度の上空を西から東に流れる風の流れそのものです。
ロスビー波は、その偏西風という流れの中で、地球の自転によって生まれる波動です。
この波動が偏西風に南北の揺れを与え、その結果として目に見える蛇行が引き起こされます。
例えるなら、偏西風が川の水そのもので、ロスビー波は川底の起伏や地球の自転という影響で川の水面に発生する「うねり」です。そのうねり(波)が、川の流れ全体を曲がりくねらせる(蛇行させる)のです。
したがって、ロスビー波は「蛇行そのもの」ではなく、蛇行を引き起こす根本的な原因となる波と理解するのが正しいです。
おまけ:海洋におけるロスビー波
大気だけでなく、海洋でもロスビー波は存在します。海洋のロスビー波は、水温躍層(水温が急激に変化する層)を上下させながら伝播し、エルニーニョ現象の発生・終息サイクルなど、海洋の変動にも深く関与しています。
このように、ロスビー波は地球の自転という根本的な物理法則によって引き起こされ、私たちの日常生活に大きな影響を与える気象・海洋現象の背後にある、非常に重要な要素なのです。
結論:ロスビー波を一言で!
長々と書きましたが・・・
ロスビー波は「偏西風の蛇行の素」!
一言で言えました。
最初からそう言えよ・・・的な。木綿なさい。