この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
対流圏から熱圏までの鉛直構造に関する知識は基本中の基本。
気温の変化や紫外線との関係も必須です。
あなたの知識の確認のため、ぜひミニテストを活用してください!
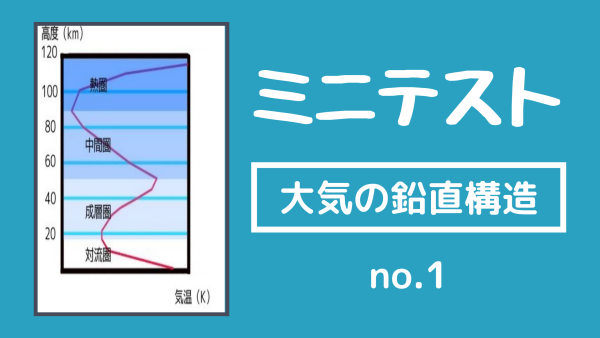
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
対流圏から熱圏までの鉛直構造に関する知識は基本中の基本。
気温の変化や紫外線との関係も必須です。
あなたの知識の確認のため、ぜひミニテストを活用してください!