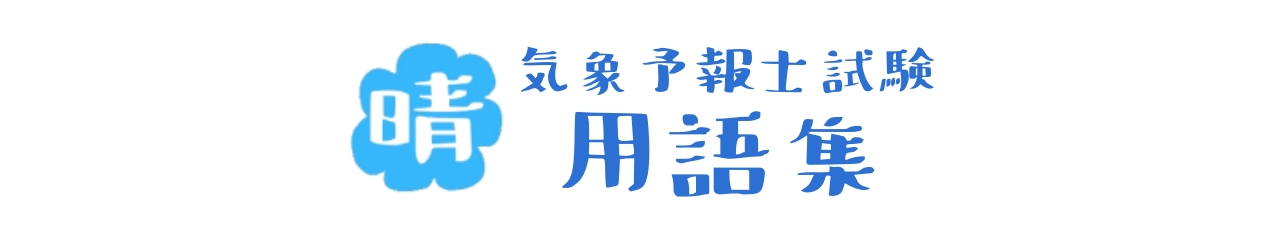ロスビー波(Rossby wave)とは、地球規模の大気の流れや海洋の動きに見られる、非常に大きな波のこと。
気象学や海洋学において、「惑星波(planetary wave)」とも呼ばれ、地球の自転がその発生と伝播の鍵を握っている。
ロスビー波は、中緯度に吹く偏西風の流れに現れる大きな蛇行(波)である。
大気の大規模な波動の一種で、偏西風がまっすぐでなくなる原因でもある。
中緯度の大気は、南北に温度差がある(傾圧性がある)ため、これを解消しようとする力が働く。
その結果として、「傾圧不安定波(=ロスビー波)」が発生し、南の暖気は北上、北の寒気は南下して波のような構造ができる。
コリオリ力の緯度変化(ベータ効果)
地球が自転しているため、運動する物体には「コリオリの力」という見かけの力が働く。
この力は、北半球では進行方向の右向きに、南半球では左向きに働く。
重要なのは、このコリオリの力が緯度によって異なる(赤道で最も弱く、極に近づくほど強くなる)こと。
この緯度によるコリオリ力の変化(これを「ベータ効果」と呼びます)が、ロスビー波の発生と伝播の復元力となる。
もう少し詳しく言うと、大気の塊(あるいは海水)が南北に動こうとすると、コリオリ力の緯度変化によって、もとの緯度に戻ろうとする力が働き、これが波として伝播していくことで発生する。
波長は約 2,000 〜 5,000kmと非常に大きい。
偏西風の蛇行そのものであり、日本の天気(高気圧や低気圧の位置や移動)に大きく関わる。
温帯低気圧の発生・発達にも関係しており、天気の周期的変化や異常気象にも関係する。
発見者: スウェーデンの気象学者カール=グスタフ・A・ロスビーによって、1939年にその存在が理論的に導き出されたため、「ロスビー波」と名付けられた。
試験対策用「ロスビー波」をまとめています。
↓ ↓ ↓
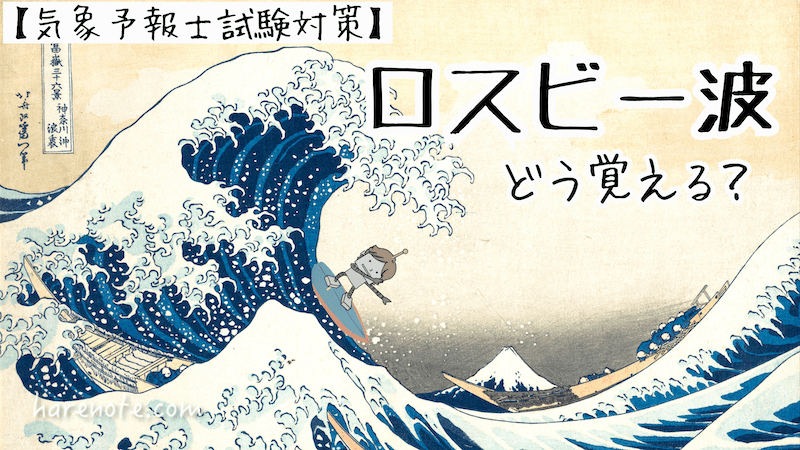
▼他の用語を検索する▼