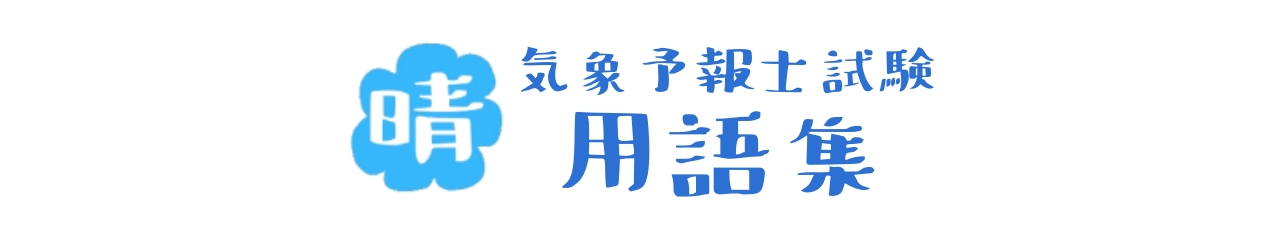大気潮汐(Atmospheric Tide)とは、地球の大気全体が、海洋の潮汐と同じように、主に太陽と月の引力や、太陽放射による大気の加熱によって、周期的に上下・東西南北に振動する現象のこと。
これは地球規模で生じる大規模な波動現象であり、主に気圧、風速、気温が周期的に変動します。
🌞 大気潮汐の主な種類と原因
海洋の潮汐と異なり、大気潮汐の主要な駆動源は太陽による熱的な加熱です。
| 潮汐の種類 | 周期 | 主な原因 | 観測される現象 |
|---|---|---|---|
| 太陽熱潮汐 (Solar Thermal Tides) | 12時間(半日周潮) | 大気中の水蒸気とオゾンによる太陽放射の吸収。特にオゾンによる成層圏での加熱が支配的。 | 赤道付近で最大1〜2 hPa程度の気圧の規則的な変動。 |
| 太陽引力潮汐 (Solar Gravitational Tides) | 12時間(半日周潮) | 太陽の引力。 | 熱潮汐に比べて非常に微弱。 |
| 太陰引力潮汐 (Lunar Gravitational Tides) | 12.42時間(太陰半日周潮) | 月の引力。 | 熱潮汐より小さいが、観測可能。 |
なぜ12時間周期が強いのか
最も強い潮汐が12時間周期(半日周潮)である理由は、太陽による加熱が「昼間(暖かい)」と「夜間(冷たい)」のサイクルを1日2回繰り返すためです。
特に、この半日周潮の振動モードは、大気の固有振動の周期と近いため、共鳴が起こりやすく、効率よく増幅されます。
📈 大気潮汐の特性
1. 伝播と振幅の増大
- 大気潮汐は地表付近の対流圏で発生し、上向きに鉛直伝播していきます。
- 上空へ行くほど大気の密度が小さくなるため、波のエネルギーを維持しようとして、潮汐に伴う風や気温の振幅は指数関数的に大きくなります。
- これにより、中間圏や熱圏では、風や気温の変動が数十メートル毎秒、数十ケルビンにも達し、上層大気の構造を決定づける重要な要因となります。
2. 日常での観測
低緯度(熱帯)地域では、太陽半日周潮の気圧変動が非常に規則的で、日中の気温変化に伴う不規則な気圧変化よりも目立つため、天気予報をしなくても気圧計を見るだけで時刻がある程度わかるほどです。中緯度では、低気圧・高気圧の通過による気圧変化の方が大きいため、大気潮汐を日常的に感じることはほとんどありません。
▼他の用語を検索する▼