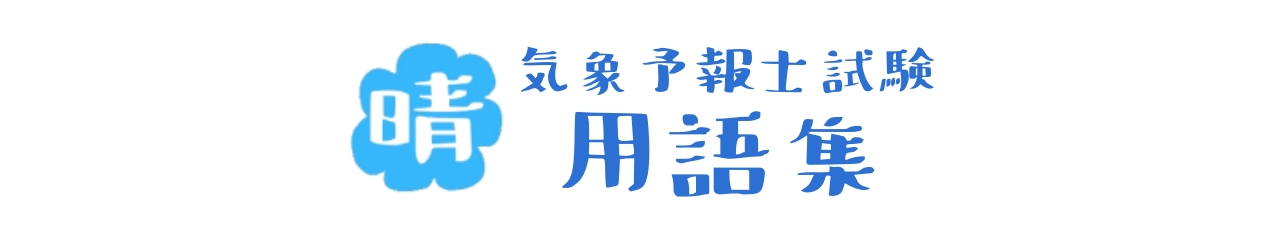ウィンドプロファイラとは、風の立体的な流れがわかるドップラーレーダーのこと。
具体的には、電波を使って上空の風向・風速を観測する機器で、ドップラー効果を利用して上空の風を観測するレーダーです。
一般的な気象レーダーが雨粒や雪を観測するのに対し、ウィンドプロファイラは、大気中の目に見えないごくわずかな乱れ(空気の屈折率の不均一性)を観測し、その動きから風の情報を得ています。
これにより、降水がない晴天時でも上空の風を連続的に測定することが可能です。
- 観測対象: 降水粒子ではなく、大気中の乱流。
- 得られる情報: 地上から上空にかけての風向・風速の鉛直分布(風のプロファイル)。
- 観測頻度: リアルタイムで高頻度な観測が可能。
このため、天気予報や航空機の運航支援など、上空の風の情報が不可欠な分野で重要な役割を担っています。
ウィンドプロファイラの観測は、以下のステップで行われます。
- 電波の発射: 地上に設置されたアンテナから、パルス状の電波を上空に向けて発射します。
この電波は、通常、垂直方向と、天頂から少し傾いた東西南北の計5方向(機種によっては異なる場合があります)に発射されます。 - 散乱波の受信: 発射された電波は、大気中の「屈折率の不均一」な部分(例えば、温度や水蒸気量のわずかな違いによる乱流)によって散乱されます。
また、雨や雪などの降水粒子がある場合は、それらからも電波が強く散乱されて戻ってきます。 - ドップラー効果の解析: 散乱して戻ってきた電波の周波数のずれを測定します。
この周波数のずれは、電波を散乱させた大気の乱れや降水粒子が、観測点に対してどのくらいの速さで動いているか(視線速度)を示します。これがドップラー効果です。 - 風速の算出: 5方向から得られたそれぞれの視線速度のデータを組み合わせて、三次元的な風のベクトル(風向・風速)を計算します。
- データ出力: この一連のプロセスを10分間隔で繰り返し、各高度の風向・風速のデータとして出力します。
これにより、地表から最大で12km程度までの上空の風の鉛直分布がリアルタイムでわかります。
雨や雪が降っている場合は、降水粒子からの散乱波が非常に強くなるため、より高い高度まで観測が可能になります。
しかし、この場合は観測データが降水粒子の移動速度に影響されるため、データ解析にその影響を考慮する必要があります。
ウィンドプロファイラの観測は、時間と空間の両方において、非常に高密度なデータを提供します。
ウィンドプロファイラは、10分間隔で上空の風を観測しています。
従来のラジオゾンデ観測が1日2回(午前9時と午後9時)であったことを考えると、この高頻度な観測は、風の時間変化を詳細に捉える上で革命的です。特に、前線の通過や局地的な突風など、急激な気象変化の監視に非常に役立ちます。
高度方向(鉛直分解能)
高度方向の分解能は、機種によって異なりますが、一般的に200〜300m間隔で風の情報が得られます。
これにより、地上から数kmの上空まで、多層にわたる風の構造を把握できます。
降水がある場合は、より高い高度(約7〜12km)まで観測できることがあります。
地理的な広さ
気象庁が運用するウィンドプロファイラ観測網「WINDAS(ウィンダス)」は、全国に33地点が設置されており、日本列島の広範囲をカバーしています。
この観測網は、地上のアメダス(地域気象観測システム)に対し、「空のアメダス」とも呼ばれています。
| 観測項目 | 間隔・分解能 |
|---|---|
| 時間 | 10分間隔 |
| 高度 | 200〜300m間隔 |
| 観測網 | 全国33地点 |
この高密度な観測データは、数値予報モデルの精度向上や、集中豪雨・突風などの短時間予報に大きく貢献しています。
▼他の用語を検索する▼